研究会活動
研究部会
-
・情報活用研究部会
あらゆる情報をビジネスの中に効果的に活用する方法や技術・事例をテーマにした研究グループ活動
-
・システム運用研究部会
ビジネスに貢献するITサービスの実現に向けたシステム運用と管理方法に関する技術・事例をテーマにした研究グループ活動
-
・合同研究部会
開発と運用の垣根を越えた、ビジネスを支える最新技術や、開発・運用手法に関する研究グループ活動
年間スケジュール
| 2024年5月 | 春の全体会 |
|---|---|
| 2024年7・8月 | 合宿 |
| 2024年12月 | 冬の全体会 |
| 2025年1・2月 | 発表練習会 |
| 2025年3月 | シンポジウム |
※各日程については追ってお知らせいたします。
※以上内容以外に、グループごとに会合を実施
研究活動内容
-
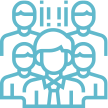
メンバ数約6~8名程度で
研究グループを構成 -

ユニリタの担当が
コーディネータとして参加 -
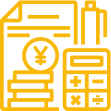
活動に沿って「グループ活動費」を支給(書籍代・会合費など)
※別途イベント参加費(シンポジウム・合宿・懇親会費用など)が発生します。
参加条件
| ・UNIRITAユーザ会会員であること。
ユーザ会主催のイベントは対面開催となりますが、研究会活動についてはオンラインとなる場合があります。 ※原則自身が所属する地区を選択し、参加してください。 |
その他
|
研究会活動の各種イベントには以下の費用が掛かります。 ・春の全体会:懇親会費(3,000円) ・合同合宿:参加費(18,000円程度)+交通費(開催場所:研究部会地区近郊予定) ・冬の全体会:懇親会費(3,000円) ・ユーザシンポジウム:参加費(2023年度実績68,000円(*))+交通費(開催場所:調整中) (*)開催方法により前後することがございます。あらかじめご了承ください。 |
募集期間
2024年3月25日(月)~2024年5月7日(火)
研究テーマ一覧
ご希望の地区を選択してください
-
東日本地区 | 情報活用研究部会
これからのIT
参加者は情報システム部やITベンダのマネジメント層の方が対象です。
ITの課題に対する最新技術による解決策や導入実績を相互に提供し合う、会社を離れた情報交換の場を提供していきます。また、メンバの豊富な経験を活かし、ユーザ会に参加する研究部会メンバへの支援を行います。
本研究グループは複数年参加を基本とし、研究や発表というスタイルを取りません。
(2023年度IE01からの継続) -
東日本地区 | 情報活用研究部会
生成AIの新たな活用法
近年生成AIが世界中で注目されており、ビジネスでの利用も広まってきています。すでにいくつかの業種では成功事例も出ており、今後のさらなる活用に期待が持たれています。
これまで生成AIの活用があまり進んでいない業種に注目し、そのような業種の企業が上手く利用するために必要なことや考慮すべきことは何かを実際に生成AIを使用して検証を行い活用方法を模索します。 -
東日本地区 | 情報活用研究部会
BizDevOpsとデザイン思考
デザイン思考とは、デザイナーの思考プロセスを活用して課題解決を行うための思考法です。デザイン思考で作った構想を、BizDevOpsで開発から運用まで落とし込むためにはどのようなプロセスが必要となるか。
BizDevOpsとデザイン思考について研究します。 -
東日本地区 | 情報活用研究部会
XRを利用したマーケティングの可能性
XRとは、現実世界と仮想空間を融合することで、現実世界にはないものを体験することができる技術の総称です。
ARやVR、MRなどをマーケティングに活用することができるかを模索・研究します。 -
東日本地区 | 情報活用研究部会
2025年の崖を見据えたアジャイル開発
レガシーシステムが残存することによって発生する様々な課題の対応のため、DXの推進が進まない可能性があり、これによる経済損失を「2025年の崖」と呼びます。アジャイル開発によって、レガシーシステムの刷新における言語・データのコンバージョンをどのように実現できるか。
2025年の崖を乗り越えるためのアジャイル開発について研究します。 -
東日本地区 | 情報活用研究部会
世代とダイバーシティ
デジタルネイティブであるZ世代は考え方や価値観が他の世代とは異なると言われています。また、個人の特性を重視したダイバーシティも企業価値を上げるには重要であると叫ばれるようになりました。
後天的にデジタルに触れてきたX世代、デジタルとともに成長したY世代の考え方や価値観、時代背景を今一度分析しつつ、様々な世代がそれぞれの特性を活かして共同して働くための理想の姿はどのようなものかについて議論、研究します。 -
東日本地区 | 情報活用研究部会
令和時代のUI/UX
我々が日々利用するデバイスは、PCやスマートフォン、タブレット、スマートウォッチなど、日々多様化しています。
昨今のデバイスの変化に対応した最適なUIやUXについて研究します。 -
東日本地区 | 情報活用研究部会
今から始めるDX
DXと言われても何から始めれば良いかわからない、人材が不足して遂行できない、既存業務を変えられないなど、様々な悩みがあって着手できない企業も多くあります。
こういった企業において現実的な範囲でDX的事業の企画、提案、実行はどうなされるべきかを研究します。 -
東日本地区 | 情報活用研究部会
IT業界のカーボンニュートラルを考える
地球温暖化は世界規模で深刻なテーマとなっており、SDGsにも組み込まれるなどカーボンニュートラルは先進国ではより強い義務感を持って取り組むべきテーマとされています。
工業や流通業など、CO2排出に直接的な関わりがある業界では高い関心を持たれているが、IT業界でも何か貢献できることはないのか。IT業界のカーボンニュートラルについて研究します。 -
東日本地区 | 情報活用研究部会
システム開発のスキル継承
スクラッチ開発からパッケージ開発、さらにはクラウドを活用したサービス開発まで、システム開発に求められる役割やスキルは何か。
それらを今一度棚卸しし、これから来るIT人材不足の中、その継承や今後のあるべき姿について研究します。
-
東日本地区 | システム運用研究部会
運用管理事例
参加者は、情報システム部やITベンダ、メーカのマネジメント層の方を対象とします。 ITの課題に対する最新技術による解決策や参加企業を含めた様々な業態の導入事例、実績を相互に提供し合う、会社を離れた情報交換の場を提供していきます。また、メンバの豊富な経験を活かし、ユーザ会に参加する研究部会メンバへの支援を行います。
本研究グループは、複数年参加を基本とし、研究や発表というスタイルを取りません。 (2023年度OE01からの継続) -
東日本地区 | システム運用研究部会
DX時代のSRE体制
デジタルビジネスを支えるために、これまでの社内システムの運用体制とは異なるスピード感が求められます。
IT部門や事業部門も含めて、どのような体制・運用が望ましいかを研究します。 -
東日本地区 | システム運用研究部会
目指すべき運用人材像とキャリアプラン
運用のアウトソーシングが増えていく中、運用メンバはどのように変わっていく必要があるか。
会社としてどのようなキヤリアプランを策定していく必要があるかを研究します。 -
東日本地区 | システム運用研究部会
セキュリティを考慮して生成 AI などを活用するために最適な運用とは
※AI TRiSMの活用方法ChatGPTなどの技術が発展し、様々な業務で効率化が進んでいく可能性が高いと思われます。一方で、生成AIの活用は、セキュリティや情報漏洩リスクなども存在します。
そのようなリスクをどのように排除していくべきかを研究します。 -
東日本地区 | システム運用研究部会
運用業務で利用するChatBotや生成AIの有効活用方法
運用組織・業務で最新技術のChatBotや生成AIをどのように活用すると有効性があるかを研究します。 -
東日本地区 | システム運用研究部会
メインフレーム人材のスキルシフト研究
富士通ホストの撤退が世の中をにぎわせる中、これまでメインフレームの運用を実施してきたメンバをどのようなスキルシフトをさせるべきか・人材活用するべきかを研究します。 -
東日本地区 | システム運用研究部会
システム部門の期待変化と今後の役割
デジタルビジネス・社内システムなど様々な領域でITが活用される中、情報システム部門はどのような役割を担っていくべきかを研究します。 -
東日本地区 | システム運用研究部会
運用引継ぎのDX対応(デジタル化)研究
運用引継ぎは、これまでアナログ(人・OJT・ドキュメント活用など)な引継ぎ方法が多かったが、デジタル技術を活用し、最適かつ効率的な引継ぎ方法を研究します。 -
東日本地区 | システム運用研究部会
運用現場からのカスタマーサクセス活動研究
運用組織が考えるべき「カスタマーサクセス」とは何か。
カスタマーサクセス活動を通して、運用組織がどのようなことに貢献するかを研究します。 -
東日本地区 | システム運用研究部会
ゼロトラスト実現に向けて運用組織が考えるべきこと
ゼロトラストを実現する為に様々な組織と連携し、また様々なツールを駆使して、環境を整える必要があります。
運用組織として、ゼロトラストの実現に向けて、考えておくべきことを研究します。
-
中部地区 | 情報活用研究部会
業務へのAI活用
近年、AIの技術はさまざまな分野で活用が進んでいます。AIを活用できれば業務効率化や生産性の向上、コスト削減などが実現可能です。一方でAI技術は幅広く使い方も多様であるため、AIをどのように活用していけば、業務に役立てていけるかを研究します。
-
中部地区 | システム運用研究部会
運用DXへの取り組み
システムのオープン化やクラウドの活用に伴い、運用部門ではコストや工数削減を図っています。一方で、サービス品質の向上や業務の属人化、アナログ作業などはいまだ課題でもあります。
このような課題を解決するための手法として、運用部門として今取り組むべきDXについて研究します。
-
西日本地区 | 合同研究部会
業務変革とIT活用
参加者は情報システム部やITベンダのマネジメント層の方が対象です。
IT全般についての問題・課題や活用方法を情報交換しながら、解決策をディスカッションする会社を超えた情報交換の場になります。
また、本年度はシンポジウムでパネルディスカッションを行います。 -
西日本地区 | 合同研究部会
AI TRiSMを学び生成AIを正しく活用する方法
AI TRiSM(=信頼性、リスク管理、セキュリティの枠組み)を用いて、生成AIの倫理的かつ責任ある使用方法に焦点を当てます。
生成AIの社会への統合を促進する為、また誤用によるリスクを最小限に抑える為のガイドラインの開発を目指します。
AI技術の進化、法的規制、社会的受容性にも対応するための研究を行ないます。 -
西日本地区 | 合同研究部会
デジタル技術を利用した自動化システムの市民化
デジタル技術を用いた自動化システムが社会にもたらす影響を研究します。
職場における自動化の可能性を、市民開発とその技術から探り、社会や産業の構造にどのように組み込まれるかを検討します。
また自動化技術のメリット(社会的・経済的)の最大化を目指す研究を行い、市民化を実現する為のデジタルリテラシーの向上、すべての人々が利用できるその開発推進を目指します。 -
西日本地区 | 合同研究部会
AI活用で業務ミスをなくすIT運用最適化の実現
AI技術の進化に伴い、IT運用の効率化と業務ミスの削減を目指し、新らしいスタンダードの形成を研究します。
特に、業務プロセスにおけるヒューマンエラーの識別と自動リカバリを通じて、省力化の実現と共に運用の質向上を模索するテーマです。
事例研究、プロセス改善、運用自動化のためのアルゴリズム開発が主な研究内容です。 -
西日本地区 | 合同研究部会
AI拡張型開発による次世代システム構築の新潮流
AI拡張型開発の研究を通じて、AIを用いた設計、プログラミング、コード生成、バグの検出と修正、開発作業の予測といった、具体的なタスクを支援する方法の研究を行います。
開発者にとっては、AIでは難しく複雑で創造的な問題解決に集中できる環境の実現を目指します。 -
西日本地区 | 合同研究部会
アジャイル開発を活用したDXの加速と成果の最大化
DXにおけるアジャイル開発手法の適用とその成果の最大化を研究します。
組織の柔軟性、市場への迅速な対応、および継続的なイノベーションを可能にするアジャイル手法の具体的な実装戦略をについて考え、これらの要素がDXの成功にどのように寄与するかを明らかにすることを目指します。 -
西日本地区 | 合同研究部会
コミュニケーションの深化がもたらす心理的安全性とチーム生産性への効果
組織内コミュニケーションの質の向上と、それがチームの心理的安全性及び生産性に与える影響を分析します。
対話の技術、およびチームメンバ間の信頼関係の構築に重点を置きます。
組織が人材の能力を最大限に引き出し、チームの生産性を高めるための研究を行ないます。
-
九州地区 | 合同研究部会
生成AIを活用した業務効率化
生成AIを用いることで、自動化や処理時間の短縮、サポート時間の拡張、意思決定の迅速化、多様なアイデアの生成など、従来の業務プロセスに革新をもたらすことが可能です。業務の効率化を目的として、生成AIを活用した業務改善や顧客エンゲージメント向上に関するアイデアを創出し、業務活用に向けた研究を行います。










