研究会活動
研究部会
-
・情報活用研究部会
あらゆる情報をビジネスの中に効果的に活用する方法や
-
技術・事例をテーマにした研究グループ活動
-
・システム運用研究部会
ビジネスに貢献するITサービスの実現に向けた
-
システム運用と管理方法に関する技術・事例をテーマにした研究グループ活動
- ・合同研究部会/研究部会
- 情報活用研究部会とシステム運用研究部会が連携して協力する
- 技術・事例をテーマにした研究グループ活動
-
年間スケジュール
2025年5月 春の全体会 2025年7・8月 合宿 2025年12月 冬の全体会 2026年1・2月 発表練習会 2026年3月 シンポジウム ※各日程については追ってお知らせいたします。
※以上内容以外に、グループごとに定期的に会合を実施しています。研究活動内容
各研究部会では、1年間を通じてテーマごとに研究グループ活動を行い、
ユーザシンポジウムで研究成果を発表します。
また、春は研究グループのキックオフ、冬は研究の進捗報告および研究グループ相互の情報交換を目的とした全体会を地区毎に実施し、
親睦を深めるための懇親会を適宜行います。
-
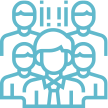
-
メンバ数約6~8名程度で研究グループを構成
-

-
ユニリタの担当がコーディネータとして参加
(主にコーディネータ・サブコーディネータの二名体制) -
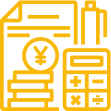
-
活動に沿って「グループ活動費」を支給(書籍代・会合費など)
※別途イベント参加費(シンポジウム・合宿・懇親会費用など)が発生します。
参加条件
・UNIRITAユーザ会会員企業であること。
・研究会活動のイベントや会合に、可能な限り参加できること。※ユーザ会主催のイベントは対面開催となりますが、
研究活動については、グループごとに対面・リモートを活用して実施しています。
※原則自身が所属する地区を選択し、参加してください。その他
研究会活動の各種イベントには以下の費用が掛かります。
・春の全体会:懇親会費(3,000円)
・合同合宿:参加費(20,000円程度)+交通費(開催場所:研究部会地区近郊予定)
・冬の全体会:懇親会費(3,000円)
・ユーザシンポジウム:参加費(※2024年度実績74,000円(シングル))+交通費
※開催場所・方法により前後することがございます。あらかじめご了承ください。募集期間
~2025/5/9(金)17:00まで
※申込受付を終了いたしました。研究テーマ一覧
ご希望の地区を選択してください
-
東日本地区 | 情報活用研究部会
これからのIT
参加者は情報システム部やITベンダーのマネジメント層の方が対象です。
ITの課題に対する最新技術による解決策や導入実績を相互に提供し合う、会社を離れた情報交換の場を提供していきます。
また、メンバの豊富な経験を活かし、ユーザ会に参加する研究部会メンバへの支援を行います。
本研究グループは複数年参加を基本とし、研究や発表というスタイルを取りません。
※(2024年度IE01からの継続) -
東日本地区 | 情報活用研究部会
AI時代に必要なデータガバナンス
生成AIの進化が加速する中、ビジネスでの活用が広がる一方、学習データの質とガバナンスの重要性が増しています。
本研究グループでは、AI時代に求められるデータガバナンスの理想像を探求し、より公平で信頼性の高いデータ活用の在り方を研究します。
若手、中堅以上の方向け -
東日本地区 | 情報活用研究部会
量子コンピュータの現実的な可能性について考える
量子コンピュータの実用化には課題があるものの、実用事例が生まれ始め、未来への期待が高まっています。
本研究グループでは、量子コンピュータの活用が可能な分野や得意とする問題領域を探求し、その可能性を深く研究します。
若手、中堅以上の方向け -
東日本地区 | 情報活用研究部会
「2025年の崖」を迎えた変化
日本企業が市場で勝ち抜くためにはDXの推進が必要不可欠として「2025年の崖」という表現で注意喚起されましたが、2025年を迎えた今、各企業での対応状況や変化を検証し、今からでも回避できる方法を研究します。
若手、中堅以上の方向け -
東日本地区 | 情報活用研究部会
データドリブン経営の実現
消費者行動の多様化が進む中、データを活用した経営の重要性が高まっています。
本研究グループでは、膨大なデータを分析し、行動予測を経営に活かすデータドリブン経営の実現方法を研究します。
若手、中堅以上の方向け -
東日本地区 | 情報活用研究部会
生成AIとエンジニアの共存
生成AIの進化により、エンジニア業務の一部が代替されつつあります。
これからの時代、エンジニアにはどのようなスキルが求められるのか?業務の棲み分けやAIの活用法を探り、エンジニアの将来像を研究します。
若手、中堅以上の方向け -
東日本地区 | 情報活用研究部会
システム開発における画像生成AI活用
生成AIの進化により、コード生成だけでなく図の作成も可能になり、設計業務への活用が期待されています。
本研究グループでは、構成図などの設計書作成における画像生成AIの活用範囲や効果的な利用方法を研究します。
若手、中堅以上の方向け -
東日本地区 | 情報活用研究部会
農業分野におけるIT活用
少子高齢化や担い手不足が進む中、農業の効率化が急務となっています。
IoTやAI、リモートセンサーなどのIT技術がもたらす変化に注目し、農業分野を支援する技術の活用方法を研究します。
若手、中堅以上の方向け -
東日本地区 | 情報活用研究部会
令和時代におけるサイバーセキュリティおよびBCP対策
デジタル化の進展に伴い、サイバー攻撃はますます高度化・複雑化しています。令和時代の企業には、セキュリティ強化とBCP策定が不可欠です。
本研究グループでは、サイバー攻撃への対応策や業務継続を可能にするBCPの構築方法を研究します。
若手、中堅以上の方向け -
東日本地区 | 情報活用研究部会
人とコンピュータの相互作用
UI、UX、デザイン思考など、ユーザビリティを重視した開発の必要性が高まっている中、多様なデバイスの利用も進んでいます。
本研究グループでは、人とコンピュータの間に生じる「相互作用」に焦点を当て、その効果的なデザインと体験の向上について研究しています。
若手、中堅以上の方向け -
東日本地区 | 情報活用研究部会
健康・福祉を支援するテクノロジー
SDGs目標3「すべての人に健康と福祉を」の実現に向け、世界中でさまざまな取り組みが進められています。
本研究グループでは、ITを活用した健康・福祉を支援する取り組みについて調査し、その可能性について研究します。
若手、中堅以上の方向け
-
東日本地区 | システム運用研究部会
運用管理事例
参加者は、情報システム部やITベンダー、メーカのマネジメント層の方を対象とします。
ITの課題に対する最新技術による解決策や参加企業を含めた様々な業態の導入事例、実績を相互に提供し合う、会社を離れた情報交換の場を提供していきます。
また、メンバの豊富な経験を活かし、ユーザ会に参加する研究部会メンバへの支援を行います。
本研究グループは複数年参加を基本とし、研究や発表というスタイルを取りません。
※部門⾧・マネージャーの方向け(2024年度OE01からの継続) -
東日本地区 | システム運用研究部会
引継ぎレスの実現
運用業務の引継ぎは、多くの企業にとって⾧年の課題です。
従来の研究では「ドキュメント整備」や「OJTの改善」が主な解決策でしたが、本研究グループでは、より効率的な方法や引継ぎそのものを不要にする可能性を研究します。
若手、中堅以上の方向け -
東日本地区 | システム運用研究部会
運用現場が描く未来の運用ビジネス
2030年にはIT人材不足が最大80万人規模に達すると予測される中、企業は自動化など限られたリソースでの運用効率化に取り組んでいます。
本研究グループでは、ITベンダーやユーザ企業の視点から運用ノウハウを活かし、新たなビジネス展開の可能性を研究します。
※ 運用業務の経験のある方向け -
東日本地区 | システム運用研究部会
SX・DX・レガシー、マルチ環境時代のIT運用標準化
企業はサステナビリティやDXを掲げ、価値向上に取り組む一方、レガシーシステムの運用も依然として課題となっています。
本研究グループでは、新旧システムを適切に運用し、企業価値を高めるためのIT活用の在り方を研究します。
若手、中堅以上の方向け -
東日本地区 | システム運用研究部会
セキュリティリスク対策の運用最前線
ランサムウェアの脅威が常に存在する中、脆弱性を定期的に見極め対応することが不可欠です。
本研究グループでは、他社の事例や金融庁の情報を分析し、運用の観点から効果的な脆弱性確認の方法を研究します。
若手、中堅以上の方向け -
東日本地区 | システム運用研究部会
運用現場から考えるサステナブルIT
「サステナブル」という言葉は一般的になりましたが、運用現場での具体的な貢献方法は明確ではありません。
本研究グループでは、最先端のサステナブルITの事例を調査し、運用現場で実践可能な取り組みを研究します。
若手、中堅以上の方向け -
東日本地区 | システム運用研究部会
脱インシデント対応!
~障害・問い合わせを根本からなくすには~インシデント対応は常に課題であり、これまで対策が検討されてきましたが、根本解決には至っていません。
本研究グループでは、障害や問い合わせを根本からなくすことをテーマに掲げ、持続的な解決策を研究します。
若手、中堅以上の方向け -
東日本地区 | システム運用研究部会
限られた人材で実現する持続可能な業務運用
日本では労働人口の減少が深刻な課題となっています。
本研究グループでは、人材不足のリスクにどのように対応すべきかを考察し、限られた人材を活用しながら業務を安定的に継続するための具体策を研究します。
若手、中堅以上の方向け -
東日本地区 | システム運用研究部会
パブリッククラウド活用による運用効率化
企業はこれまでオンプレミスやプライベートクラウドを用途に応じて活用してきましたが、パブリッククラウドの運用も重要性を増しています。
本研究グループでは、運用現場の効率化やクラウド採用時の注意点をテーマに研究します。
若手、中堅以上の方向け -
東日本地区 | システム運用研究部会
システムの安定運用を支える共創の鍵
システムの品質維持や安定稼働は、自社だけでは限界があります。
本研究グループでは、関係者と共創し、持続可能な運用を実現するための具体策を研究します。
※中堅以上
-
中部地区 | 情報活用研究部会
AI活用によるIT人材不足へのアプローチ
近年、AI技術はさまざまな分野で活用が進んでいます。AIを活用できればIT人材不足の解消にも繋がる可能性があります。
一方、単にAIを導入するだけで本当の意味で人手不足を解消できるかという課題もあります。
本研究グループでは、AIによるIT人材不足解決へどのようなアプローチを行えば実現できるか方策について研究します。
若手、中堅以上の方向け
-
中部地区 | システム運用研究部会
AI活用による運用品質向上・標準化へのアプローチ
昨今、システム運用領域にもAIの活用が注目されています。AI活用の広がりを見せる一方、システム運用業務では人による判断や作業、障害対応や復旧等の業務も多く残っています。
本研究グループでは、運用エンジニアの日々の業務に焦点をあて、AIを活用することで、品質向上や標準化が実現できるかについて研究します。
若手、中堅以上の方向け
-
西日本地区 | 西日本研究部会
業務変革とIT活用
企業におけるITの重要性は、経営からの要求が増大するにつれて年々高まっています。
人材不足を補うためのデジタルツール導入による業務効率化が進む一方で、セキュリティ強化やコスト削減など、経営者からは効率的なIT投資が求められています。
また、DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進に伴い、社員のワークライフバランスの向上や組織の変革といった多様な課題にも直面しています。
本研究グループでは、参加企業の人材不足対策やビジネス部門との連携強化、コスト管理やROI(投資対効果)の評価などについて、情報交流を中心に活動を進めていきます。
部門⾧、マネージャーの方向け -
西日本地区 | 西日本研究部会
AIに任せる日常業務
~自動化によるビジネス効率化の新常識~近年、多くの企業がAI(人工知能)を活用して業務の自動化を進めています。AIを使うと、人が手作業で行っていた作業をより早く効率よく進めることができます。
AI活用にあたり、AIがどうやって判断しているのか、そのプロセスを理解することは非常に重要であり、企業がAIを安心して使えるようになります。
本研究グループでは、AIツールやワークフロー自動化ツールを使って実際の仕事に適用してみます。あなたの部署の業務の悩み、AIで解決できるかも!AIツールを活用した新しい働き方を、みんなで一緒に見つけていきませんか?
業務効率化を展開したいIT部門の方や、知識は無いがITを活用したい部門の方もぜひご参加ください。
若手、中堅以上の方向け -
西日本地区 | 西日本研究部会
AI拡張型開発による次世代システム構築の新潮流
AI拡張型開発の研究を通じて、AIを用いた設計、プログラミング、コード生成、バグの検出と修正、開発作業の予測といった、具体的なタスクを支援する方法の研究を行います。
開発者にとっては、AIでは難しく複雑で創造的な問題解決に集中できる環境の実現を目指します。
若手、中堅以上の方向け -
西日本地区 | 西日本研究部会
サービス管理を快適に
~ITSMツール最適化で業務を加速~ITサービスマネジメント(ITSM)は、ITサービスの提供と管理を効率化するために不可欠なフレームワークです。多くの企業ではITSMツールを活用していますが、操作性や使い勝手に課題があることが多いです。
本研究グループでは、ITSMツールのユーザビリティを改善し、効率的な運用管理を実現するための手法を検討します。
ITサービス管理の基本的な理解とツールの改良による現実的な効果を学べる研究です。
若手、中堅以上の方向け -
西日本地区 | 西日本研究部会
新時代のデータ活用戦略
~ガバナンス強化で支える効率的な業務環境~デジタライゼーションの進展に伴い、企業が扱うデータの量や種類が飛躍的に増加しています。その中で、データを正確かつ一貫して管理し、適切に活用することは企業の競争力に直結します。データガバナンスは、データを安全かつ効果的に運用するための基盤であり、信頼性の高いデータがもたらす精度の高い意思決定は、業務効率の向上やリスク軽減に寄与します。
本研究グループでは、データの透明性と信頼性を確保し、デジタル時代に即したデータガバナンスの最適な手法を探求します。
若手、中堅以上の方向け -
西日本地区 | 西日本研究部会
DX推進の障壁と成功への道筋
~まだ進まないのかDX?~多くの企業がデジタルトランスフォーメーション(DX)の重要性を認識していますが、実際に推進できている企業はまだ少ないのが現状です。
特に、経営層の理解不足や推進リーダーの不在、適切なベンダーが見つからないことが大きな課題です。また、DXを成功させるための具体的なロードマップが欠如しているケースも多いです。
本研究グループでは、DX推進の障壁を明確化し、現実的な解決策を提案することで、企業が持続的な成⾧を実現するための道筋を示します。
若手、中堅以上の方向け -
西日本地区 | 西日本研究部会
ヒューマン・コンピュータ・インタラクション(HCI)の最適化
~人間とコンピュータの境界を超えるユーザーエクスペリエンス(UX)~HCIは、人間とコンピュータが効率的に連携するためのインターフェース設計に関わる分野です。
特に、操作性やデザインの微細な変化がユーザーの生産性に大きく影響します。
また昨今、音声認識やウェアラブルデバイスの活用も進んでおり、これらの要素を取り入れることでインタラクションの効率をさらに向上させることが可能です。
若手、中堅以上の方向け
-
九州地区 | 九州研究部会
HCIを活用したサービスの可能性
HCIとは、ユーザーとコンピュータのインタラクションを最適化するための重要な分野で、チャットボットによる音声の受け答えやVR、味やにおい、触覚の出力など、コンピュータと人間をつなぐ手段は広がっています。
一方デジタルデバイスやAI技術の普及に伴い、ユーザーエクスペリエンス(UX)の向上が求められていますが、ユーザの多様な特性(年齢や障害の有無など)やニーズに応えるインタフェース設計が難しく、全ての人に配慮したデザインやサービスは十分とは言えません。
このような課題を解決するために、HCIの新しい技術を使ったサービスの導入や活用方法について研究します。
一般職、運用者、技術者の方向け
※技術的な知見がない方も、利用する立場で研究に参加してください。 -
九州地区 | 九州研究部会
IT技術を駆使したウェルビーイングの促進
ウェルビーイングは、心身の健康や幸福感を指し、テクノロジーがその向上に寄与する可能性が注目されています。
ウェルビーイングを促進する技術は多様ですが、効果的な利用方法や各個人に合ったアプローチの不足、データプライバシー、セキュリティの問題などを考慮する必要があります。
センサーデバイスやAIなどの新しい技術を活用することで、身体的、精神的、社会的に満たされた状態を向上させるための研究をします。
一般職、運用者、技術者の方向け
※技術的な知見がない方も、利用する立場で研究に参加してください。
-








